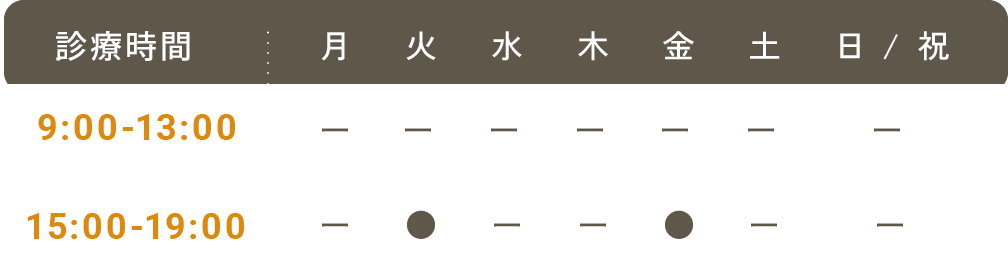糖尿病

糖尿病とは、インスリンが十分に働かないために、血液中を流れるブドウ糖(血糖)が慢性的に増えてしまう病気です。
通常は膵臓から分泌されるインスリンというホルモンによって、血糖値は適度な範囲にコントロールされ、過剰に増加しないようになっています。しかし、糖尿病になると、インスリンの作用不足によってブドウ糖が有効に使われずに、慢性的に血糖が増えてしまいます。血糖の濃度(血糖値)を高いまま放置し長期化することで、特有の合併症(心臓病や腎不全、失明、神経障害、足の病変)につながります。糖尿病には主に2つの種類があります。
1型糖尿病
原因
1型糖尿病では、膵臓でインスリンを作る細胞(β細胞)が壊れてしまう為、インスリンが膵臓からほとんど出なくなることにより、血糖値が高くなります。1型糖尿病の原因はまだ不明な点もありますが、免疫反応が正しく働かないことで、遺伝因子やウイルス感染などが誘因となり自分の細胞を攻撃してしまうこと、つまり自己免疫が関与していると考えられています。
発症年齢
若年者(小児)に多く発症のピークは思春期にあり、それ以降は男女とも発症が低下するといわれています。しかしどの年齢でも発症する可能性があり、小児だけの病気ではありません。最近の研究では1型糖尿病の1/3以上は30歳以降に発症しているといわれています。

治療
インスリン分泌不足が原因のため、生きていくためには外からインスリンを補充すること(インスリン注射)が必須です。インスリンをからだの中に取り入れる方法は、日本では今のところ注射薬のインスリンしかありません。
また、適切な食事療法と運動療法を組み合わせることにより、合併症を予防し進行を防いでいきます。
2型糖尿病
原因
2型糖尿病の発症リスクを高める因子は大きく分けて、2つあります。
ひとつは遺伝的素因によるインスリン分泌低下、もうひとつは生活習慣の悪化(肥満や食べ過ぎ、運動不足)によってインスリン分泌不足(インスリン抵抗性)になる環境的素因です。
発症年齢
主に中高年層に多いですが、最近では若年層や子供にも増加しています。
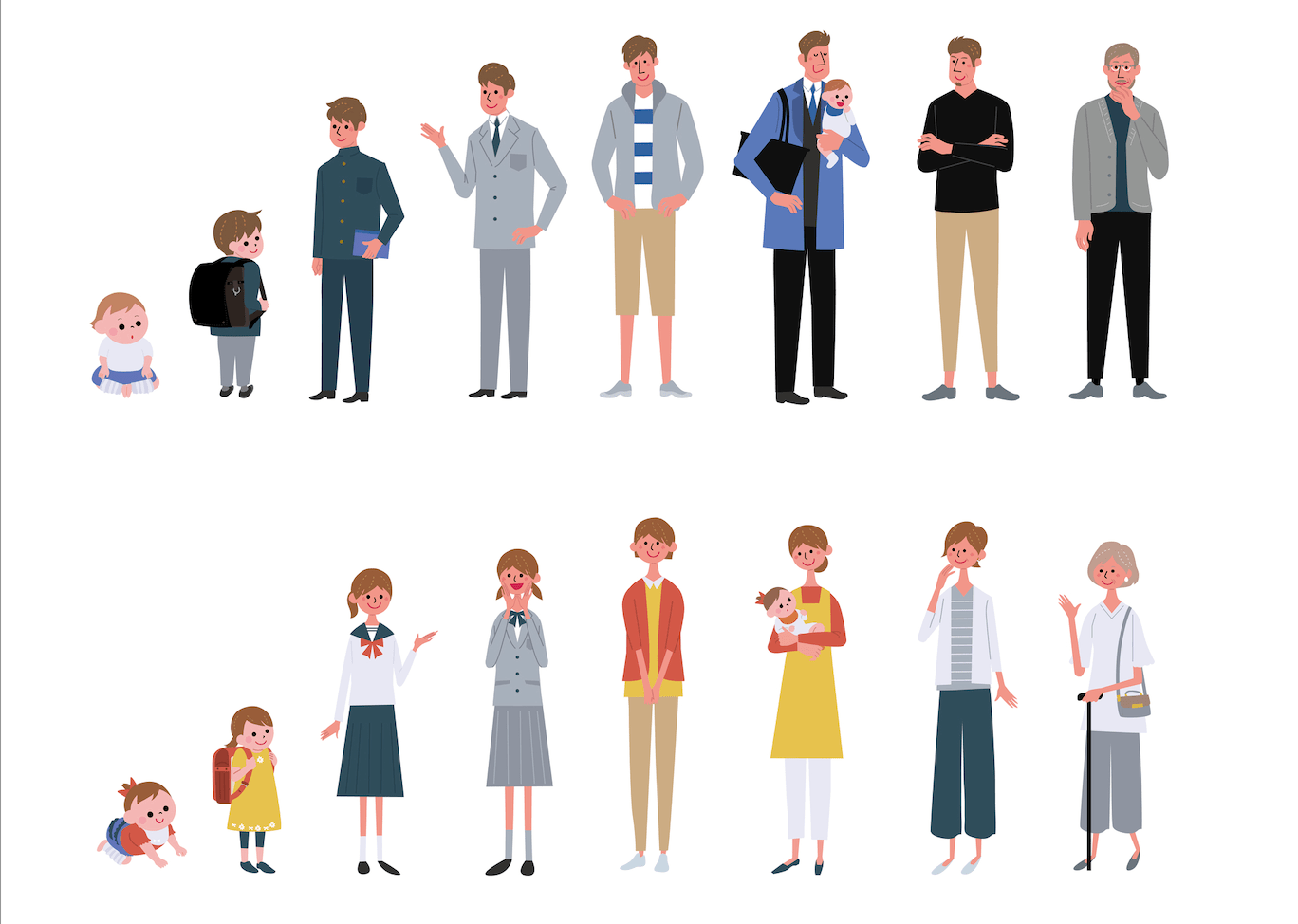
治療
2型糖尿病の治療の基本は食事療法や運動療法によってインスリンの効きをよくすることで、治療にインスリンを必要としないケースもあります。場合によっては経口薬やインスリンによる治療もおこないます。
その他
膵外分泌疾患(膵炎・腫瘍など)、内分泌疾患(Cushing症候群・先端肥大症・褐色細胞腫など)、肝疾患(慢性肝炎・肝硬変)、薬剤(グルココルチコイド、インターフェロンなど)、妊娠糖尿病など。
糖尿病の症状
糖尿病は初期段階では自覚症状がほとんどないことが多く、症状が出るとしてもごく軽いものになります。しかし、体の中では少しずつ進行していき、気が付いた時には深刻な影響を及ぼします。気になる症状があれば血糖値は血液検査で確認できますので、早期発見の為にも早めにご相談ください。
初期段階の自覚症状
のどの渇き・頻尿
血糖値が高いと、体は余分な糖を尿として排泄しようとするため、尿の量が増えます。頻尿によって体内の水分が失われるためにのどが常に渇き、さらに水を飲むというサイクルを繰り返します。
疲れやすい
何もしていないのに常にだるい、十分な睡眠をとっていても朝起きた時に疲れがとれない場合も、糖尿病の可能性があります。血糖が体内で有効に使われず、体がエネルギー不足になるため、倦怠感を感じるからです。
体重減少
たくさん食べているのに、また、いつもの食生活と変化がないのに体重が減る場合は、糖尿病の可能性があります。
血糖をエネルギーとして使えなくなり、不足したエネルギーを体内の脂肪や筋肉を消費して得ようとするため、体重が減少するためです。
視力の低下
目がかすむ、突然視力が低下する、などはもしかしたら糖尿病網膜症の可能性もあります。
傷が治りにくい
血糖が高い状態では白血球の働きが悪くなるなど、免疫機能が低下し、小さな傷でも治りが遅くなります。
糖尿病の合併症
血糖が長期間、高い状態が続くと、自覚症状がないままでも体の中では血管や神経が少しずつ傷ついていきます。そうなると以下のような深刻な合併症を引き起こす可能性があります
心筋梗塞や脳卒中
高血糖が動脈硬化の進行を早め、心筋梗塞や脳卒中のリスクが高くなります。
腎臓病
体内に不要な老廃物を尿として排泄し、必要な物は吸収するというようなフィルターのような機能が働かなくなる「糖尿病性腎症」が進行します。進行が進むと透析療法や腎移植を受けないと生きていけなくなります。
視力障害
網膜の血管が傷つき、視力が低下したり網膜剥離や視覚障害などの症状がでる「糖尿病網膜症」により、最悪の場合は失明することがあります。
神経障害
早期から自覚症状が現れやすい合併症です。高血糖の影響を受け神経が傷つき神経そのものの性質が変化し、手足のしびれや痛み、感覚の低下などの「糖尿病性神経障害」を引き起こします。
足の病変
神経障害の合併のために足の感覚が鈍くなり、傷がついても気づかずに壊疽へ進行してしまうこともあります。最終的には足を切断しなければならない場合があります。
糖尿病の治療法
糖尿病の治療の目的は、血糖コントロールによって病気の進行を予防し、糖尿病がない人と変わらない健康的な寿命を保つことです。もう一つは合併症の発生を防ぎ、合併症がある人はそれを悪化させないことです。主に以下の方法があります。

1. 生活習慣の改善
食事療法
食事療法は、糖尿病治療において必ずおこなう基本的な治療法です。栄養のバランスや適正なカロリーを計算し、正しい食習慣(規則正しい食事時間、ゆっくりとよく噛む、腹八分目でストップする、夜遅くや就寝前には食べない、脂質や塩分は控えて食物繊維をとる)を身につけて、血糖値を良好に保ちましょう。
運動療法
ウォーキングやジョギング、水泳などの有酸素運動をすることで、インスリンの効果を高めて血糖値を下げることができます。ウォーキングでは1回15~30分、1日2回、1万歩程度が目安です。また、筋力トレーニングなどの無酸素運動も適宜組み合わせることも有効です。
2. 薬物療法
薬物療法とは、お薬によって血糖をコントロールすることにより、血糖の高い症状を改善し合併症の進行を予防することを目的とします。
経口薬
2型糖尿病の治療は食事療法と運動療法ですが、これだけでは適正に体重や血糖をコントロールできない場合に使用されます。薬はインスリンを出しやすくするもの、効きやすくするもの、食事でとった糖の吸収を遅らせるもの、糖の排泄を促すものがあります。
注射製剤
1型糖尿病や、2型糖尿病でインスリン分泌が不十分な場合インスリン注射が必要です。他にインスリンの分泌を促す注射(GLP-1受容体作動薬・GIP/GLP-1受容体作動薬)があります。
3. 自己管理
血糖値・体重の測定
血糖値を定期的に測定することで、自分の血糖状態を把握し、治療計画を調整できます。また、目標体重を設定し測定などで現状を確認します。
運動の習慣
少なくとも週に3回(できれば毎日)の定期的な運動の習慣をつけるために、記録をつけたり継続しやすい仕組みを作りましょう。
医師の指導を受ける
糖尿病は慢性疾患なので、定期的な診察や検査が必要です。医師と連携し、合併症の予防や治療を行うことが重要です。